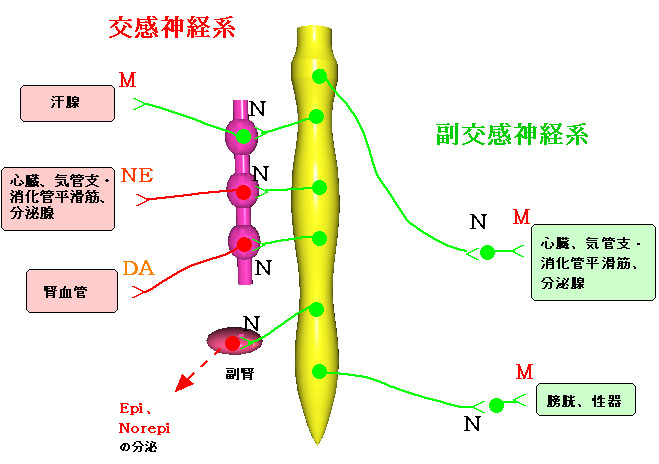
Autonomic Pharmacology(自律神経薬理学)
1898年、Langleyは自律神経という言葉を用い、交感、副交感神経に大別した。
自律神経系に働く薬物の研究により、多くの自律神経系の知識が得られた。
1、自律神経系模式図
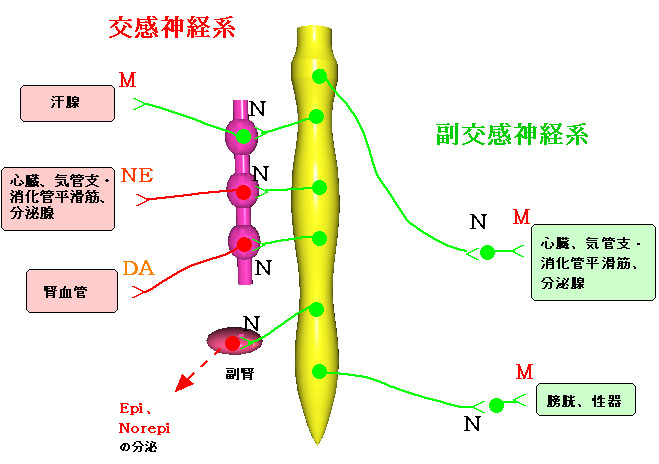
|
交感神経の節前線維は、胸髄(Th1-Th12)あるいは腰髄(L1-L3)から出る。 |
|
|
交感神経系 |
副交感神経系 |
|
節前繊維 |
短い、有髄 |
長い、有髄 |
|
節後繊維 |
長い、無髄 |
短い、無髄 |
|
神経節 |
効果器より遠い |
効果器に近い |
|
神経節でのシナプス比 |
1:20〜30 |
1:1 |
|
心臓 |
亢進(β1) |
抑制(M2) |
|
血管 |
収縮(α1) |
拡張(β2) |
|
気管支 |
弛緩(β2) |
収縮(M3) |
|
瞳孔 |
散瞳(α1) |
縮瞳(M3) |
|
消化管 |
弛緩(α2、β2) |
収縮(M3) |
|
腺分泌 |
抑制(α) |
亢進(M3) |
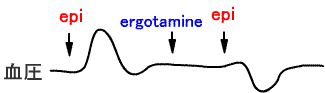
1921年 Loewiの実験:迷走神経を刺激し、心拍出量の減少した心臓(A)からの灌流液を、
別の心臓(B)に流してやると、Bの心拍出量の減少が見られた。
後に迷走神経刺激によりAChが放出されたためであることを明らかにした。
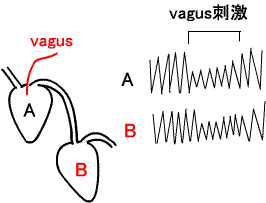
5、眼における自律神経
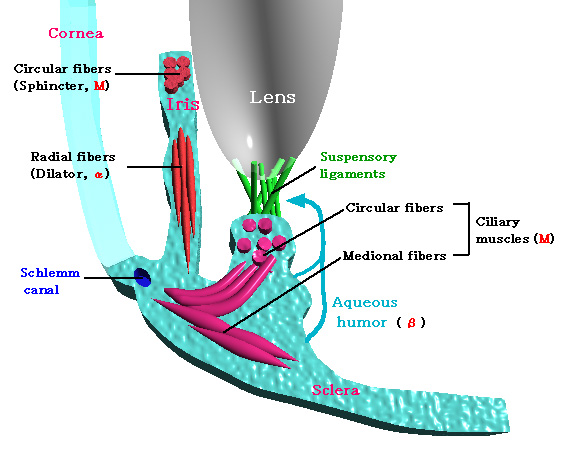
|
虹彩(Iris)には、副交感神経支配の括約筋(Circular
fibers、ムスカリン受容体(M))と |